|
|
|
|
|
|
DNAミュージックを作ろう!
作業時間:?日。方法によってさまざまです。少人数の1時間の授業で行ったことがあります。
実際に作ったDNAミュージックはこのページ下方の「結果」にて。
■ はじめに ■
- DNAは”A”,”T”,”G”,”C”というたった4種類の化学物質(核酸塩基)のつながりで成り立っています。A,T,G,Cのつながりかたによってどんなアミノ酸が指定されるかが決まります。
- たった4種類の物質からいろいろな生物が構成されている。
これって、音楽にも似ているところがありませんか?(ちょっと強引?)
- 音楽(西洋音楽)の場合、12種類の音程によって曲が成り立っています。
DNAは4種類,かたや音楽は12種類と、種類数は異なるものの、
それぞれ限られた種類から無限に近い種類の生物、または音楽が作られるのはとっても興味深いことです。
- 趣味で作曲をしているせいもあって、生徒にDNAの規則性を教えているときに、
ふとDNAを音楽を関連づけられないかと思い、DNAミュージックを考えてみました。
遺伝の授業の導入または、まとめの一環に取り入れて生徒の興味関心を高めたいというのが目的です。
- 一昔前では、インターネットもなく、パソコンの用途もそれほど幅広いものではありませんでしたが、現在では、一般の人でもDTM(デスクトップミュージック)などコンピュータを利用して曲を演奏したり、作曲したりできます。
何とか1~2時間の授業でできるようにパソコン等を利用した方法を考えてみました。
- この主旨のテーマである『DNAの塩基配列から音楽を作ろう』は、平成12年度関東理科研究発表会にて発表しました。
注意)実際にはDNAと音楽には何の相関関係もなく、
DNAミュージックは勝手に考え出した作り物であることをご理解下さい。
- 現在、DNAの塩基配列の解析が盛んに行われていますが、遺伝情報には複雑なことばかりで、到底人類にはわかり得ないことがたくさんあります。
進化の過程で複雑に形作られてきた遺伝子。
その遺伝子の中にはその生物のメッセージは込められていないのでしょうか?
非科学的な発想で考えると、空想は膨らむばかりです。
『パラサイト・イブ』という小説もそうした非科学的な空想から生み出されたのではないでしょうか!?
”遺伝子の中にその生物がおりなす音が隠されていたらいいなぁ”という興味を抱きながらDNAミュージックを考えていただけると面白みも増すと思います。
■ 用意するもの ■
- インターネットができる環境・・・塩基配列を探すため。
- パソコン・・・スピーカー必須。
- エクセル・・・変換作業を手作業で行うと大変なので、作者によるマクロプログラムがあると楽。マクロを動かすためにはエクセルが必須。
- その他・・・プリンタなど。
■ 方法 ■
- 今回の取り組みの目標は、
『DNAの塩基配列から音楽を作ることにより、タンパク質合成についての学習意欲を高める』
ことです。
あくまでも授業で行うことを目的としていますので、1~2時間の授業内で完結する内容でなくてはなりません。
そのことを踏まえて作業を次の4段階に分けました。
1)DNAの塩基配列の検索
2)塩基配列を曲データに変換
3)譜面を作成
4)演奏
これらの4段階はどれも手作業で行おうとすると膨大な時間を要してしまいます。
これを簡略化するために、コンピュータを活用することにしました。
実際に今回のテーマで生徒を募集し、課外で行ったときの様子を思い返しながら、授業への展開を考えてみたいと思います。
- DNAの塩基配列の検索

インターネットを利用してサンプルとなる塩基配列を探します。
ある程度のキーワード(DNA,塩基配列,核酸など)を生徒に与えたところ、思っていたよりも短時間(約20分)で検索できました。
ただし、塩基配列のデータベースがほとんど英語で書かれています(ちなみに日本語で書かれたものは見たことありません)。
探し当てた塩基配列の詳細について生徒から質問を受けたときに、生物名などの固有名詞は調べるのに多少時間がかかりました。
ですから、もし、授業のように生徒が数十人いて、質問の数がいくつもあるとなると、さぞかし大変だろうと思います。
もしかすると、ここから調べ学習へ移行してしまう可能性も...
- 塩基配列を曲データに変換
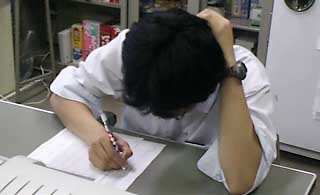
手作業で変換するとなると多大な労力と時間を要します。
パソコン(作成したマクロ)を利用すれば、塩基配列から曲データへの変換はものの数秒で完了します。
実際に生徒を交えて行ったときには、まず手作業で塩基配列を30~40個ほど変換し(それだけでも面倒)、
ある程度変換の仕方を理解した上でパソコンを利用して約1500程度の塩基配列を音符に変換しました。
- 譜面の作成
『”おたまじゃくし”はわからない!』という声は必ず起こります。
ですから、この段階は是非ともパソコンを活用するべきだと思います。
私が作成した”DNAから音符への変換マクロ”では、直接MIDIデータ(譜面)を作ることはできません。
したがって今回は”MML形式データ”を利用することにしました。
MML形式データとは、音符を文字で書いたデータのことです。
次の表に示されているのが、MML形式でかかれた音符のデータの一例です。
| g8+ a8+++ f#8 b8 c8 b8+ d8 b8 c8+ d8 r8 a8+ b8 f8 r8 g8+ |
(ちなみに”g8+”とは、「高さがソの音を八分音符の長さ2つ分だけ発音する」という意味です。)
この形式を使えば、変換マクロからデータ化することができます。
後は、MML形式データを専用のソフトウェアで演奏すれば、音楽が聴けます。
今回使用したMML形式データ対応のソフトは『サクラ』というフリーソフトです。
このソフトは無料で手にすることができ、今回大いに活用させていただきました。
この場をかりてお礼申し上げます。
(『サクラ』の著作権はクジラ飛行机(山本峰章)さんにあります。http://oto.chu.jp/)
なんだか難しい作業をしなくてはならないように感じますが、作業は5秒でできます!!
- 演奏
塩基配列から完成される音楽はメロディだけです。
これだけでも十分な音楽ですが、ちょっと格好をつけたいと思ったのでYAMAHA XGworksというソフトを使って自動伴奏をつけました。
(このソフトは体験版が配布されており、完成した曲を保存することはできませんが、自動伴奏をつけて演奏することはできます。)
譜面にしたがって楽器を弾いても構いませんが、やはり楽器を弾けない生徒でも作業できるようにするため、パソコンに演奏させました。
演奏を聴いた瞬間は、地を這うような”オー!”という感嘆の声があがりました。
■ 結果 ■
- 『Aeropyrum pernix K1は、1993年、鹿児島県トカラ列島、小宝島の浅海底硫気孔から採取された試料より、京都大学農学研究科の左子博士らによって単離された絶対好気性超好熱菌である。最適成育温度は90-95℃、最適pHは7.0、最適塩濃度は3.5%であり、従属栄養性でCrenarchaeotaに属する超好熱古細菌である』。
▼Aeropyrum Pernix
■ コメント ■
- 今回の作業はすべてパソコンで行われます。
今回の作業で、パソコンの利点は『面倒な単純作業を素早く行えること』,『マウスのクリックだけで演奏などができてしまうこと』
さらにインターネットを利用すれば、『DNAの塩基配列など特殊な情報を閲覧でき、瞬時に引き出せること』など様々です。
今回はそういった長所を活用したつもりですが、反面、パソコンには短所もあり、利用については生徒の反応を慎重に確認しながら行わなければならないと思っています。
- DNAを音楽にするという試みは、いつの頃のことかわかりませんが以前にも取り上げられていたそうです。簡易な方法として、”A,T,G,C”にそれぞれ音符を割り当てるという方法があるそうです。これは作業するのには最良の方法ですが、完成する曲は4種類の音階しか存在しません。したがって、完成する曲はどれも同じ曲に聞こえてきます。
このような単純な音の並びに神秘性を感じるという人もたくさんいるだろうし、実際にこのような試みを行うときに、単純であることが望ましいとアドバイスを頂いたこともあります。
本来、塩基配列と音楽はまったく異なるもので、両者に相関関係はありません。
こんなことを言ってしまっては身も蓋もありませんが、だからこそ変換の法則が難しかろうが、完成する曲が複雑すぎようが構わないと思います。
正しい変換の法則は存在しないのですから。
- では何が大切なのか?と考えたときに、私は「目的」ではないかと考えました。
今回の作業は、DNAの塩基配列から音楽を作ることにより、生徒のタンパク質合成についての学習意欲を高めることが第一の目的です。
ですから完成する曲は、多少複雑でも生徒にとってインパクトの強いものが良いと考えました。ただし、あまりに変換の法則が複雑すぎては、生徒は何をしているのかわからなくなり、本末転倒になってしまいますので、その辺はよく見極めなければなりません。
あくまでも学習をサポートする授業の一環であるということを踏まえ、さらに次のような目標を立てました。
1) なるべく生物種によって音楽に違いが生じるようにすること。
2) 遺伝情報の変換を間違えたときに、曲が変化したり、変化しなかったりするようにすること。
(しくみは異なりますが、遺伝子突然変異を表現したかった)
3) 作曲・編曲する力を必要とせず、楽曲が完成できるようにすること。
4) 曲が長すぎないようにすること。
5) 生徒の活動が1~2時間の授業で完結する内容であること。
以上の目標を達成しようとすると、自ずと変換法則は複雑になり、また、作業についても膨大な労力を必要としてしまいます。そのため、パソコンを活用することにしました。
パソコンを利用しながら、生徒が作業を理解して行える内容に抑えることが理想のかたちと考えたわけです。
- 少し偉そうな書いてしまいましたが、もちろん今回の変換の法則で満足しているわけではありません。これまで変換の方法について述べてきました。
説明の仕方が下手なせいもあると思いますが、一度読んだだけで理解した人はあまりいないだろうと思います。
これを生徒が理解するのも、ちょっとした時間では足りません。
もうちょっと簡単にならなかったかな?とは思います。
さらに、自分の胸中で一番の疑問点は、『果たしてこの変換方法を生徒に理解させるべきなのだろうか?』ということです。
上にも書いたとおり、塩基配列と音楽には相関関係はありません。
これまで紹介してきた変換方法は勝手に作ったものですから、はっきり言って理解する必要はないのかも知れません。
それでは何も知らないままパソコンをいじって曲を完成させるのが良いのかというとそうでもありません。
自分の結論としては『理解したつもりになる』ということで良いのではないかと思います。
例えば数人1組のグループに塩基配列を提示し、それが何の音符になるのかを答えさせる。
三人寄れば文珠の知恵といいますが、多少理解の程度があやふやな生徒の集まりでも知識を持ち寄って答えを導き出すかもしれません。
あるいは始めに問題と答えを言い放ち、どうしてそうなるのかをみんなで考えさせる。
そういった意味を込めて作ったものが”DNA学習.xls”です。
生徒が考えて理解、あるいは理解したつもりになれば、変換の法則はブラックボックスではなくなるのではないかと思います。
- 作成した変換方法は、多少の複雑さはあるものの比較的目的を捉えた方ではないかと思います。
ある変換の方法では、高さは決めるが音の長さは自由に決めて良いというものもあります。しかしその場合、楽譜を自由に読み書きできる人ならいいのですが、音符を読めない人に長さを自由に変えていいといのは酷な話です。自由さが逆に楽譜の読めない生徒を縛り付けてしまう結果をもたらすことは十分に考えられます。
そこで、今回の変換方法では音の高さと長さを決めるようにしました。
これならば誰が変換をしても同じメロディが得られます。
さらに誰にでも立派な曲ができるようにソフトウェアの自動伴奏機能を利用しました。
これによって、楽譜が読めない生徒でも格好の良い曲が、しかもあっという間に完成するのです。
問題はパソコンやソフトウェアの使い方です。
生徒に説明をして教えるのは当たり前ですが、さすがに教師1人で40人もの生徒に個別指導する時間はありませんし、
かといって、これだけマニアックな作業(DTMなど)を指導できる人はそう何人もいないだろうと思います。
目下のところ課題です。
- 生徒が作業に夢中になって、タンパク質合成との関連性を見失わないように指導することも忘れてはなりません。
目的にも書いたとおり、タンパク質合成についての学習意欲を高めるのが究極の目標ですから、作業の一つ一つを細胞内に例えることも大切です。
音符への変換を行っている”パソコン室”は”細胞”、生徒が手にしているDNA、音符へ変換している”パソコン”は”リボソーム”、できあがった”音楽”は”タンパク質”という具合です。
また、間違って入力した塩基配列からできた曲は、遺伝子突然変異によって作られた異常なタンパク質。
細胞が身近に捉えられれば幸いなことです。
- ここまで随分長たらしく書いてきましたが、『DNAの塩基配列から音楽を作ろう』の主旨や方法について理解していただけたでしょうか。
最近は話で説明することが多くなってしまったために、どうもうまく文章で説明することができません。
理解するのが大変なところもあったかもしれませんが、ご容赦願いたいと思います。
何かご意見等がありましたらメールを頂ければ幸いです。
|
|
|

