|
|
|
|
|
|
DNAミュージックを作ろう!
今回行った、塩基から音符への変換のしかたを説明します。
■ 指針 ■
- 今回は4種類の塩基を音階には定めず、次の表に示すとおり、塩基に役割を与えました。
| |
直前がリセットされている場合
(直前がT,TとAの組み合わせのとき) |
直前がリセットされていない場合
(直前がT,TとAの組み合わせ以外のとき) |
| G |
ソの八分音符 |
1音上げる (音の長さは変化しない) |
| C |
ドの八分音符 |
1音下げる (音の長さは変化しない) |
| A |
八分休符 |
音の長さを八分音符分長くする(音程は変化しない) |
| T |
連続したTの個数から1を引いた回数だけ半音ずつ変化させる。
前の音符を決定すると きに最後の塩基がGかCかによって上げるか下げるかする。
音符決定後はリセットする。 |
- ”G”と”C”は音程を変化させて主要な7音階,”A”は休符または音の長さを決定するようにし、”T”には特殊な役割を与えて12種類の音階を決定するようにしました。
- 塩基配列1~30番で曲のテンポを決定し、31番以降の塩基配列を上の表にしたがって音符に変換します。なお、完成する曲はハ長調が基準となります。
■ テンポの決定 ■
- 音符の変換の前にテンポを決定します。
塩基配列の開始地点から30番までのそれぞれの塩基の個数を数え、次の式に当てはめます。
テンポ=(Aの個数×6)+(Tの個数×5)+(Gの個数×4)+(Cの個数×3)
次のような塩基配列の場合、
| GTGCCAGGTT TGTCGGCGAG AAAAGGTACC |
Aが10個,Tが3個,Gが8個,Cが9個(計30個)ですので、
テンポ=(10×6)+(3×5)+(8×4)+(9×3)
=134
となります。
■ GとCの役割 ■
- 31番目以降の塩基配列から音符へ変換します。
以下にその説明について述べます。
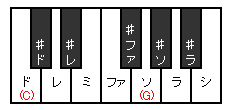
- 上の図はピアノの鍵盤です。これを参考にしながら見てください。
この変換方法では以前の音符が何だったかが重要になります。
すなわち、塩基配列の直前の音から数度音程を高くしたり低くしたりして音程を決めます。
”G”と”C”は、それぞれ音程を1音ずつ”高く”または”低く”します。
もし、以前の音程がなかった場合(以後”リセットされていた場合”と略します)、はじめに”G”がくる場合は”ソ”を指します。
さらに”G”が続いた場合は、”ラ”,”シ”,”ド”,”レ”・・・と上がり、はじめの”G”の後に”C”が続いた場合は逆に”ファ”,”ミ”,”レ”・・・と続きます。
最終的に”A”または”T”があるまで音階が変わり続けます。
一方、リセットされていた状態で、はじめに”C”がある場合は”ド”を指します。
次に”G”が続けば”G”の数だけ”レ”,”ミ”,”ファ”・・・と変化し、”C”が続けば”C”の数だけ”シ”,”ラ”,”ソ”・・・と変化します。
先ほどと同様に、”A”または”T”が出現した時点で音階が決定します。
なお、音の長さは八分音符とし、”G”や”C”がいくつ連続していても長さは”八分音符”のまま変化しません。
変換例
| GG |
ラの八分音符 |
| CC |
シの八分音符 |
| GGGGC |
シの八分音符 |
| CGG |
ミの八分音符 |

■ Aの役割 ■
- ”A”は、直前の音がリセットされているかどうかによって役割が異なりますが、基本的に音の長さを決定します。
まず直前がリセットされいる場合、”A”がはじめにあった場合、Aは”八分休符”を指します。
さらにAが続いていれば八分休符に八分休符を合わせ、四分休符になります。
”AAA”のようにAが連続してあった場合、”八分休符+八分休符+八分休符”=”付点四分休符”となり、Aの数だけ八分休符が続くことになります。
音の長さについてわからない方は、下に示した「音の長さ」の表を参考にしてください。
次に直前がリセットされていない場合、直前の音の長さに八分音符分の長さを加えます。
例えば”GGAAA”のような場合、はじめの”GG”で”ラの八分音符”となります。
後ろの”AAA”で”ラの八分音符+八分音符+八分音符+八分音符”=”ラの二分音符”が決定されます。
”G”,”C”または”T”が出現した時点で音符の長さが決定します。
変換例
| GGA |
ラの四分音符 |
| CCAA |
シの付点四分音符 |
| AA |
四分休符 |
| CGA |
レの四分音符 |
参考)音の長さ
| 1小節 |
| 八分音符 |
|
|
|
|
|
|
|
| 四分音符 |
|
|
|
|
|
|
| 付点四分音符 |
|
|
|
|
|
| 二分音符 |
|
|
|
|
| (四分音符+八分音符) |
|
|
|
| 付点二分音符 |
|
|
| (付点二分音符+八分音符) |
|
| 全音符 |
★Tの役割★
最後に”T”の役割です。
この”T”は主要な7音(ド,レ,ミ,ファ,ソ,ラ,シ)以外の5音(♯ド,♯レ,♯ファ,♯ソ,♯ラ)を決定する可能性を持ちます。
”T”が必ず主要な7音以外の5音を決定してしまっては曲がめちゃくちゃになってしまいますので、あくまでも可能性を持つに過ぎません。
そのしくみは次の通りです。
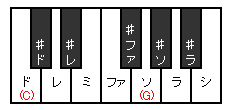
”T”は直前の音符とのつなぎをリセットします。
例えば”GAG”と”GATG”を見比べてください。
後者は間に”T”があります。
前者の場合について見てみると、はじめの”GA”で”ソの四分音符”が決定されます。
次の”GA”のとき、直前の音程が”ソ”だったので”ラの八分音符”となり、結果的に前者の場合は”ソの四分音符,ラの八分音符”が決定されます。
後者の場合、はじめの”GA”は前者のときと同じように”ソの四分音符”が決定されます。
次に”T”が挟まれているので、先ほど決定された”ソの四分音符”との関連性はなし(リセット)ということになります。
したがって、次にある”G”で”ソの八分音符が”決定され、結果的に後者の場合は”ソの四分音符,ソの八分音符”が決定されます。
これが”T”が単独存在した場合の役割です。
次に”TT”などのように”T”が複数連続して存在した場合について説明します。
”T”が複数で存在していた場合、最後の”T”を除いた”T”の数だけ半音ずつ上下に音階を変化させます。
半音ずつ上げるか,下げるかは、直前の塩基が”G”か”C”によって決まります。
例えば”GTT”のような場合、はじめの”G”でソの八分音符が指定されます。次の”T”で半音上がり、最後の”T”でリセットとなります。
したがって”GTT”は”♯ソの八分音符”となります。
一方、直前が”C”である”CTTT”の場合は、はじめの”C”で”ドの八分音符”が指定され、
次とその次の”T”で”ドからシ”,”シから♯ラ”と半音ずつ下がり、最後の”T”でリセットとなります。
(音楽的に、シとド,ミとファのように間に黒鍵がない音階は半音=1音と見なされる)
また、”GTTA”のように”T”が連続して存在して後に”A”が続く場合は、リセットする前に音の長さに加えます。
したがって”GTTA”は”♯ソの四分音符”になります。(”♯ソの八分音符,八分休符”にはなりません。)
なお、直前の音がすでにリセットされていた場合は、その後”T”が単独あるいは複数で存在しても役割を持ちません。
例)TATTTGの場合、はじめのTAで八分休符、最後の”G”でソの八分音符。間の”TTT”は役割を持たないので無視する。
変換例
| CGTT |
♯レの八分音符 |
| CCTT |
♯ラの八分音符 |
| CTTA |
シの四分音符 |
| TTTA |
八分休符 |
|
|
|

